 TOMO LABO
TOMO LABO消防士の採用試験合格に特化したオンラインスクール「東消塾」を運営しているTOMO LABOです。
消防士といえば、「休日出動もあって休みが少ない仕事」というイメージを持つ人も多いでしょう。
実際に消防士はどのくらい休みのある仕事なのでしょうか。
消防士になろうか迷っている人のために、今回の記事では消防士の休日について詳しく解説していきます。
「休みがちゃんと取れるか心配で、消防士になる踏ん切りがつかない…」という人は、ぜひ最後までご覧ください。
\試験に関する無料相談も受付中/
実は消防士の休みは驚くほど多い


休みが少ないというイメージを持たれがちな消防士ですが、実はけっこう休みが多い職業です。
令和4年におこなわれた厚生労働省の調査によると、令和3年(2021年)における1企業の平均年間休日総数は107日、労働者1人の平均年間休日総数は115.3日となっています。
これに対して、消防士は年間240日前後が休み、つまり1年の約2/3が休みということです。
なぜこんなにも休日が多いのか、その理由は、消防士が「交代制勤務」であることに隠されています。
休みは多いが1日の拘束時間が長い交代制勤務
交代制勤務は、朝8時30分から次の日の朝8時40分まで消防署で勤務し、24時間休み(非番)がもらえるという勤務形態です。



署によっては、朝9時から次の日の朝9時まで、というところもあります!
一見、24時間続けて業務をしているように感じますが、仮眠・休憩の時間も含むため、実質16時間程度の勤務時間となっています。
基本的に、消防士のひと月の出勤日数は11日前後です。
しかし1日の実働時間が長いため、ひと月単位の実働時間で考えると、実は他の職業との違いはそこまでありません。
交代制勤務を取る消防士の1日のスケジュール



以下のスケジュールは、私が実際に消防士として働いていたときのスケジュールです!
前日に働いていた消防士と交代し、業務を引き継ぐ。
消防車や消防車に積んでいる資機材の点検をおこなう。
前日から引き継いだ事項の共有や、その日の業務内容に関することを話し合う。
隊ごとに別々の業務をおこなう。
- 机上業務
救助活動の報告書や、火災の原因に関する報告書を作成する。 - 立入検査
スーパーや学校など、あらゆる施設に行き、消防用設備の点検をする。
災害が発生時に迅速な消防活動ができるよう、放水・救助・危険物取り扱いなどの訓練をおこなう。
隊ごとに別々の業務をおこなう。
- 机上業務
その日の業務の報告書や日誌を作成し、次の日に業務をおこなう隊への引き継ぎ事項をまとめておく。司令室での119番対応もする。 - 勉強・トレーニング等
消防活動に関する勉強や、消防署が通れるルートの再確認等をおこなう。また、円滑な救助活動をするために必要な筋力トレーニングをする。 - 車庫警備
消防車庫内で点検や警備作業をおこなう。
仮眠室で仮眠をするが、いつ出動要請があってもいいように、活動服のまま寝る。
引き継ぎのための事務処理や、消防署内や車庫内の清掃をおこなう。
次の隊が使う車両や車庫、資機材の点検もしておく。
必要事項を次の隊へ引き継ぐ。
これで1日の業務が終了となる。
夜中に火災があった場合などは、残業で火災調査などが入ることもある。
業務が終了し次第、この日は非番となる。
紹介したスケジュールはあくまで一例なので、勤める消防本部によって若干の違いがあります。
また、このスケジュールは非常事態が起こっていない場合のスケジュールです。
夜間や朝方に出動要請があれば、その分勤務時間も伸びる可能性があることを念頭に置きましょう。
それでは、上記の交代制勤務のスケジュールをふまえて、消防士の主な勤務形態である「2交代制」と「3交代制」について解説していきます。
「2交代制」の場合の休日サイクル
「2交代制」とは、当直と非番を1日おきに繰り返す勤務形態です。
全国の消防士の約半数が、この「2交代制」となります。
勤務日と休日サイクルは、以下のカレンダーをご覧ください。


「2交代制」は、基本的には1日働いたら1日休み(非番)で、さらに週休が2日挟まるというサイクルです。
「非番」は、災害等で呼び出しがかかることがある待機の日です。
100%休みというわけではありませんが、出動することは滅多にありません。
「週休」は、一般企業の土日休みと同様に、完全に休みの日になります。
「3交代制」の場合の休日サイクル
「3交代制」とは、当直と非番を繰り返し、一定期間で日勤が入る勤務形態です。
全国の消防士の約3割が、この「3交代制」となります。
勤務日と休日サイクルは、以下のカレンダーをご覧ください。


「3交代制」は、非番の日を休日とみなせば、1日働いたら2日休みというサイクルです。
月に1日もしくは2日ある「日勤」は、一般企業の勤務時間と同様に朝から夕方まで働く日で、デスクワークが中心となります。
一般企業と同じ働き方の「毎日勤務」をする消防官もいる
実は消防士の中でも、交代勤務制を取らない、一般企業と同じ働き方をする人もいます。
これは「毎日勤務」という勤務制度で、現場には一切出ず、デスクワークのみをおこなう事務部門の担当です。
消防士全体で見ても、「毎日勤務」をする消防士は約2割しかいません。
土日で完全週休2日、月から金までの日勤となり、一般的な労働者とまったく同じリズムで仕事をします。
有給を使えば休みはさらに多くなる
消防士は公務員なので、年間20日の有給休暇が与えられます。
希望日に確実に取れるわけではありませんが、国のための仕事ということもあり、有給が取れないということは絶対にありません。
「2交代制」や「3交代制」であれば、非番と週休と合わせて有給を使うことで、年に何度も長期休暇を作り出すことも可能です。
休みの多さだけを理由に消防士になるのはやめておこう


ここまでで、交代制勤務の消防士は休みの日数が多いことがわかりました。
しかし、休みが多いからといって安易に消防士になろうとするのは危険です。
理想と現実のギャップに戸惑ってしまうかもしれませんし、なにより人の命を救う仕事なので、生半可な気持ちでは務まりません。
休みの多さだけで消防士になってはいけない理由について、詳しく解説していきます。
思っていたより休みが少なくなる場合がある
「ひと月に11日しか出勤しなくていい」という考えは捨てましょう。
これは、非番の日にも非常事態で呼び出されたり、消防に関する行事や訓練に呼ばれたりするからです。
滅多にあることではありませんが、それでも「思っていたよりも休みが少ない!」と感じてしまう要因ではあります。
消防士は人の命を救う仕事なので、それなりの責任感が必要です。
そのため、まずは休日の多さよりも、本当にやりたい仕事なのかどうかを考えてから消防士を目指しましょう。
休みは多いが決して楽な仕事ではない
休みの日数だけ見ると楽な仕事のように感じてしまいますが、業務内容は過酷です。
災害が起こったときには命をかけて消防活動をおこなう必要がありますし、特に事件が多発する都市部の消防署では、さまざまな業務で多忙を極めます。
さらに、当直・非番・休日の生活リズムがそれぞれ変わってしまうと、体内時計をまた戻すのにもひと苦労。
体力のない人だと、日々の激務や不規則な生活による疲れで休みの日は何もできず、結局充実した休日は送れなかったという人も出てくるでしょう。
消防士が実際にしている非番や週休の過ごし方


消防士は日々大変な業務をこなしているため、休みの日には心身ともに労ることが大切です。
以下では、消防士が休みに何をしているのかについて紹介します。



休みの日の使い方も、消防士にとってはとても重要です!
家でしっかりと身体を休める
当直が終わったばかりの非番の日は、身体がぐったりとしています。
そのため、次の当直に万全な状態で臨めるよう、まずはしっかりと身体を休ませることが大切。
とはいえ、ただダラダラと寝て過ごすと、あっという間に次の当直になってしまうため、休みはしつつもできるだけ有意義に過ごすことを心がけている人が多かった印象です。



私が家で休むときには、映画やドラマを観たり、読書をしたり、ゲームをしたりと、さまざまな方法で休んでいました。
趣味を楽しむ
非番や週休の日を趣味に使うと、日々の業務から頭が離れてリフレッシュできます。
業務を離れてもトレーニングが趣味の人や、身体を動かすアウトドアが趣味の人もいれば、美術館に行って静かに過ごす人など、さまざまです。
中には消防の知識やスキルを高めるため、休みの日まで勉強をするという人までいました。



モチベーションが高い同僚でしたが、本人からすると、勉強も趣味の一環のようです。
家族との時間を大切にする
消防士は、非番の日は出動要請があればすぐにでも出勤しなければいけません。
さらに、週休といっても土日ではないことがほとんど。
一見すると家族との時間が取りづらいと思われがちですが、非番や週休と合わせて有給も使えば、かなり多くの休みを取ることも可能です。
そのため、意外と家族との時間は多めに取れます。
家族と過ごすとツライこともすべて忘れられるため、多忙で過酷な業務をこなす消防士にとって、本当に重要な時間です。
消防士の休みに関するQ&A
消防士の休みに関してよくある質問をまとめました。
消防士の休日数についてのまとめ
一般的なイメージとして、消防士はハードワークで休みがあまり取れないと思われがちです。
しかし、出勤日数だけでいえば月に11日前後と、他の仕事よりも少なくなっています。
1日あたりの拘束時間は長いですが、仮眠の時間も含まれているため、24時間まったく寝られないわけではありません。
非番と週休をうまく使えば、プライベートの時間もたくさん確保できるはず。
もしこの記事を読んで「消防士になろうと思った!」という人は、私が運営する、消防士の合格に特化したオンラインスクール「東消塾」もぜひご覧ください。



難関と言われる消防士試験。
もし悩みがあれば無料で相談も受け付けています!
\試験に関する情報を定期的に発信中/
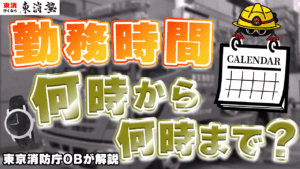
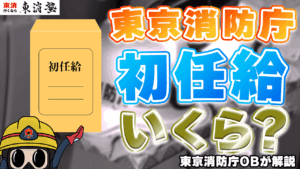



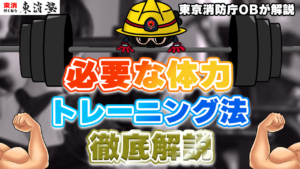
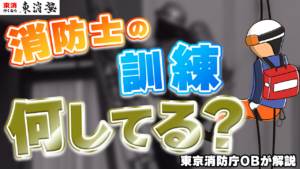
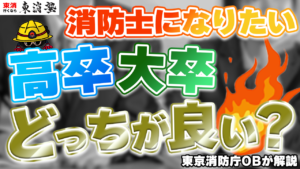

コメント