 TOMO LABO
TOMO LABO消防士になるためのオンラインスクール「東消塾」の講師と代表を務めるTOMO LABOです。
「小論文試験対策を始めたけど、どんな対策をしていいのかわからない」という悩みを持っている受験生は多いことでしょう。
小論文試験の傾向と対策を掴むためには、過去問を調べることが非常に有効です。
そこで今回の記事では、東京消防庁の小論文試験の過去問を紹介し、傾向と対策について解説していきます。
本気で一次試験に合格したい人は、ぜひ最後までご覧ください。
\消防士採用試験に合格したい人はこちら/
小論文試験の傾向と対策を理解する方法
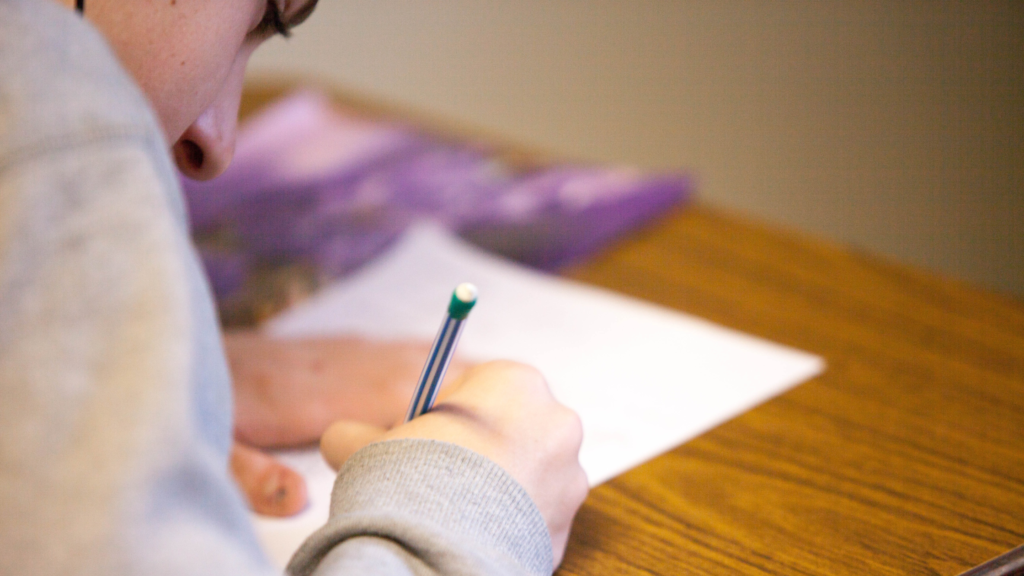
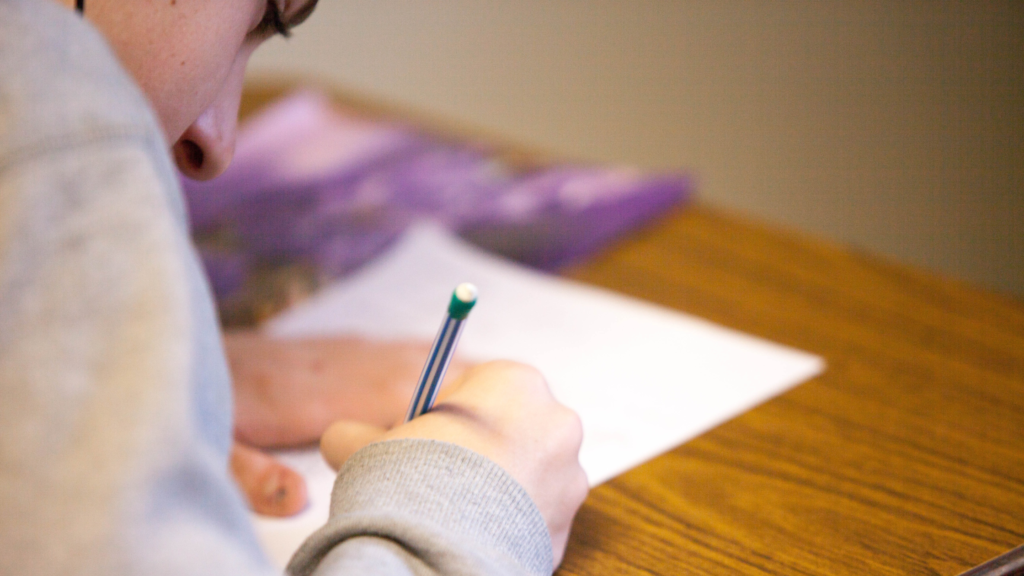
小論文試験は毎年出題されるテーマが変わるため、傾向を掴むことが非常に難しくなっています。
しかし、過去問をもとにある程度の傾向を知れば、対策を立てることが可能です。



傾向をもとに対策を立てる方法を、以下にまとめました!
小論文を書き始める前に、過去にどのようなテーマで出題されたのかをまとめましょう。
最低でも、過去5年分は見ておくと良いですね。
この時点で書き始めても「書き方の練習」にはなりますが、傾向が掴めていないため、まったく予想していない問題が出たときに困ってしまいます。
ある程度過去問が確認できたら、どのような出題ジャンルがあるのかを分類してみましょう。
分類の仕方の例を、以下にまとめました。
- 災害・防災について
- チームワークや仕事について
- 自分自身について
- 社会問題について
ある程度出題ジャンルを分類できたら、近年ではどのジャンルの出題が増え、逆にどのジャンルの出題が減っているのかを見てみましょう。
そうすることで、近年の試験の傾向が掴めます。
出題が増えてきているジャンルがわかったら、そのジャンルに絞って優先的に対策していきます。
出題傾向がわかり、対策目標が明確になったら、ようやく小論文を書き始めます。
小論文の基本的な書き方を勉強し、その後、必ず第三者からフィードバックを貰いましょう。
1人で書いてもなかなか上達は難しいので、小論文だけ対策してもらいたいという人は、「東消塾」へ相談することも候補に入れてみてください。
東京消防庁小論文試験の基本的な対策について詳しく知りたい方は、以下の表を参考にしてください。
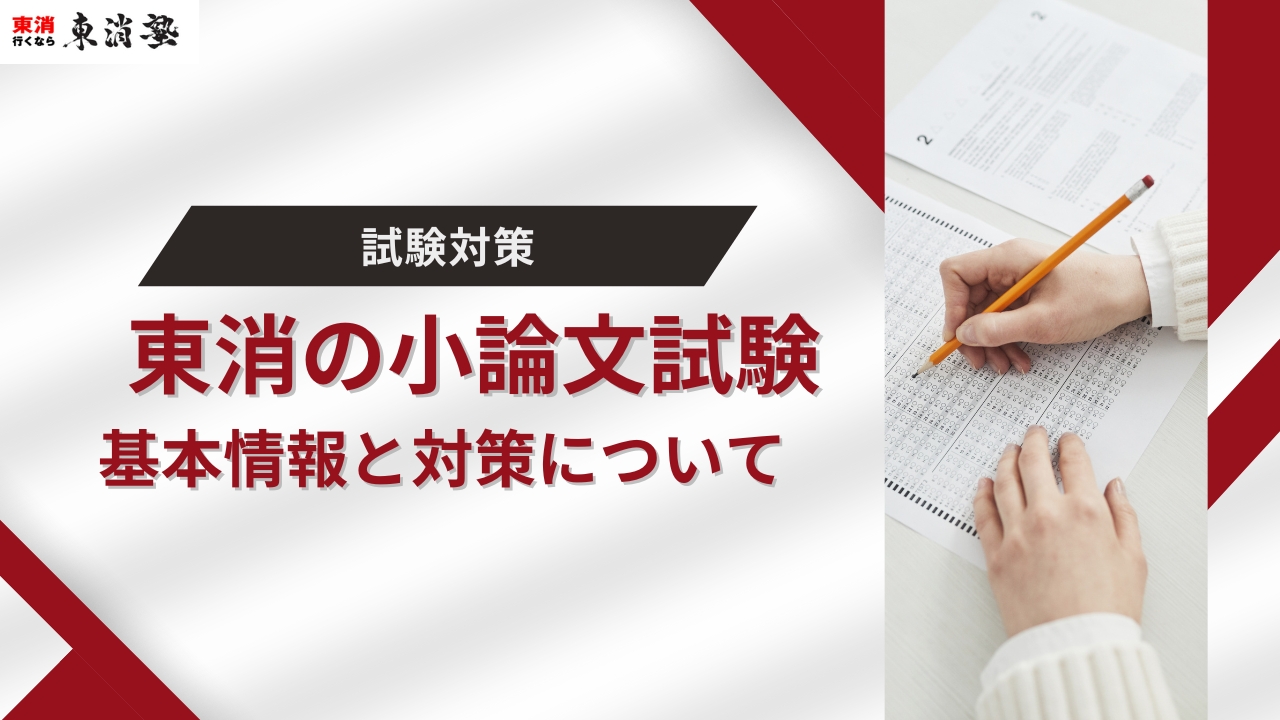
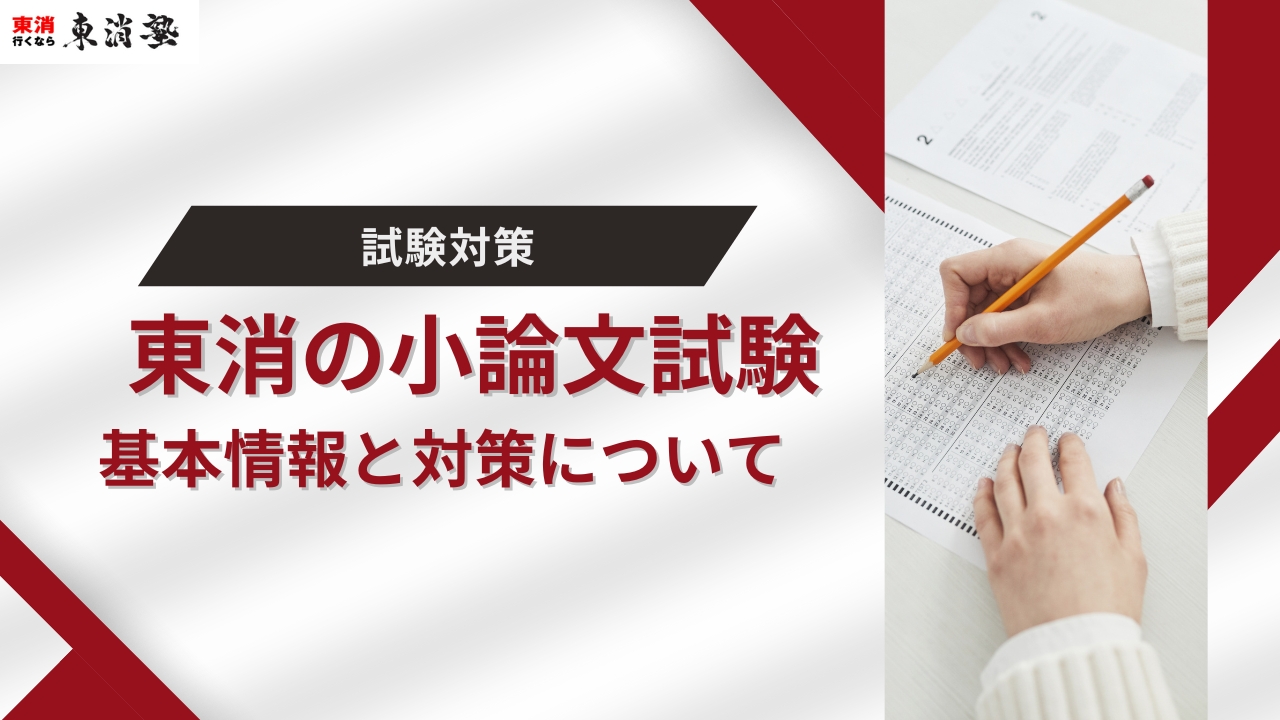
東京消防庁で実際に出題された小論文の過去問テーマ


東京消防庁採用試験にて、過去5年で実際に出題された小論文のテーマをご紹介します。
なお、今回ご紹介するのは1類試験と2類試験からです。
東京消防庁Ⅰ類試験(令和元年~令和5年度)の過去問
- 令和6年度
-
- 都民が東京消防庁に期待することをあげ、その期待に応えるために東京消防庁が行うべき施策についてあなたの考えを述べよ。(1回目)
- 消防職員に高い倫理観が求められる理由をあげ、消防職員として都民の信頼を得るためにあなたが取り組むことを述べよ。(2回目)
- 令和5年度
-
- 消防職員の使命についてあなたの考えとその達成に向けてあなたができることを述べよ。(1回目)
- 東京消防庁の職員に求められる倫理観や規律の遵守が求められる理由についてあなたの考えを述べよ。(2回目)
- 令和4年度
-
- 都民から信頼される消防官となるために、あなたが実践することを具体的に述べよ。(1回目)
- 今後の社会情勢を踏まえ、質の高い行政サービスを提供するために、消防官としてあなたが取り組むことを述べよ。(2回目)
- 令和3年度
-
- デジタルトランスフォーメーション(DX)の実現が人間社会にどのような影響を与えるのか、あなたの考えを具体的に述べなさい。(1回目のみ実施)
- 令和2年度
-
- 下の資料(省略)から傾向を読み取り、行政機関が発信する情報を都民に広く周知するための効果的な方法を考え、具体的に述べなさい。(1回目)
- 社会人として必要なものを3つ挙げ、それを身に付けるためにあなたが今後どう取り組んでいくのか具体的に述べよ。(2回目)



Ⅰ類試験は、資料やグラフから読み取れる問題が多いですね!それらを正確に読み取るスキルも必要なことがわかります。
東京消防庁Ⅱ類試験(平成30年度~令和4年度)の過去問
令和5年度試験以降、Ⅱ類試験は実施されなくなりましたが、参考にはなるため一応記載しておきます。
- 令和4年度
-
- 東京消防庁の職員として大切だと思うことを、今までの経験を踏まえて述べなさい。
- 令和3年度
-
- 官公庁がソーシャルネットワーキングサービス(SNS)を積極的に活用することの利点とその活用方策、さらにその際に注意すべきことを具体的に述べなさい。
- 令和2年度
-
- あなたの経験から「失敗を糧に成長できた」と考えられる事柄をあげ、今後当庁で仕事をしていくうえでそれをどのように生かしていくのか、あなたの考えを具体的に述べなさい。
- 令和元年度
-
- 職場におけるチームワークの重要性とチームワークの醸成に対する取り組み方について、あなたの考えを具体的に述べなさい。
- 平成30年度
-
- SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)が社会に与える影響についてメリットとデメリットを挙げ、それに対するあなたの考えを具体的に述べなさい。



過去5年で2回もSNSについて出題されているのが気になりますね。あとは単純に、事象に対して自分がどう思うかが問われています。
東京消防庁Ⅲ類試験(令和元年~令和5年度)の過去問
- 令和6年度
-
- あなたが感じる東京消防庁の魅力と、消防職員としてどのように成長していきたいかについて述べよ。
- 令和5年度
-
- あなたが東京消防庁を希望する理由と、どのように成長していきたいかを述べよ。
- 令和4年度
-
- 東京消防庁の職員として、10年後のあなたがどんな成長を遂げているか述べなさい。
- 令和3年度
-
- 自ら考えて行動するために日頃から行うべきことを具体的に述べなさい。
- 令和2年度
-
- あなたの経験から「失敗を糧にして成長できた」と考えられる事柄を挙げ、今後当庁で仕事をしていくうえでそれをどのように生かしていくのか、あなたの考えを具体的に述べなさい。



Ⅲ類試験では、「東京消防庁で働くこと」についての出題が多いですね!未来へのビジョンや、自身がなぜ東京消防庁を選んだのか、今一度しっかりと考えてみましょう!
【令和7年度】東京消防庁小論文試験のテーマ予想


東京消防庁小論文試験のテーマは、試験当日まで公表されません。そのため「確実にこれが出題される」と言い切ることは不可能です。
しかし、過去問から今年の小論文のテーマを予想することは可能です。具体的には、以下の内容のどれかから出題される可能性が高いと考えています。
- 消防官や社会人としてあるべき姿や考え方
- 過去の災害やそれに対する対策について
- 東京都や東京消防庁が行っている取り組みについて
特に出題される可能性が高いのは「消防官や社会人としてあるべき姿や考え方」についてです。東京消防庁においては、Ⅰ類とⅢ類どちらも受験者自身に関するテーマが出題されています。
小論文試験に臨む際は、自己分析を徹底的に行っておくのとともに、東京都や東京消防庁の取り組みに関することも調べておくことが大切です。



テーマを1つに予想するのは不可能ですが、傾向を絞ることは可能です!
小論文試験で模範解答をするためのおすすめの方法


小論文試験で模範解答をするためのおすすめの方法は、以下の3つです。
- 小論文が減点方式だと理解する
- 予備校を活用する
- 小論文に関する参考書で対策する
小論文で模範解答をするためには、独学で対策するよりもノウハウを理解した上で対策することが大切です。知っているだけで模範解答に近づけるものも多いため、小論文試験対策をする前に必ず確認しておきましょう。



この方法を試すだけで他の受験者よりも一歩リードできます!
小論文が減点方式だと理解する
小論文試験で模範解答するためにも、小論文は減点方式だと理解しておきましょう。満点を目指せるように意識するのではなく、凡ミスを抑えて平均点以上を確実に取ることが大切です。
小論文試験の減点部分としては、以下のようなものが挙げられます。
- 誤字脱字がないか
- 丁寧に書く努力をしているか
- 文字の表記方法にミスがないか
- 文章構成がおかしくないか
- 末尾の表現が統一されているか
上記はほんの一例であり、代表的な減点部分です。上記は意識すれば直せる部分であり、該当部分を減らすだけでも平均点以上を狙えます。
また「字が下手だからそれだけで減点だ」と感じる方もいるでしょう。しかし、小論文試験では字の綺麗さよりも丁寧に書く努力をしているかを見ています。そのため、適当に書き殴るのではなく、丁寧に書く努力をすることが大切です。
予備校を活用する
小論文試験で模範解答するためには、予備校を活用するのがおすすめです。予備校には、受験する消防本部の過去問だけでなく、過去に合格した方の小論文のお手本が揃っています。
過去の合格者の小論文を参考にすることで、小論文の質を高めることが可能です。
小論文試験合格のために予備校を活用しようと考えている方は「東消塾」がおすすめです。東消塾は消防官採用試験合格に特化した予備校であり、講師には消防士OBの方もいます。
また、LINE公式アカウントを追加することで限定特典を受け取ることができ、小論文試験のコツについても知れるため、一度無料登録してみるのがおすすめです。
小論文に関する参考書で対策する
小論文試験で模範解答するためには、小論文に関する参考書で対策するのもおすすめです。中でも「完全攻略 東京消防庁の消防官採用試験 小論文・面接試験編」は、東京消防庁OBの方が執筆されており、実体験をもとにした重要なポイントが全て網羅されています。
具体的なテクニックや模範解答例なども掲載されているため、手軽に対策できる参考書としておすすめです。
また、小論文試験だけでなく、面接試験の対策に関しても網羅されているため、とりあえずこの1冊を持っておけば間違いありません。
消防官採用試験に関するおすすめの参考書について知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。


傾向と対策の注意点


ここまで傾向と対策に関してお話をしてきましたが、これらはあくまでも推測でしかありません。
実際に次年度に出題される問題を知っているのは東京消防庁や各消防本部の試験官のみです。
そのため、傾向と対策を掴んで「これだけやればいいんだ!」というような安直な考えはせず、しっかりと戦略を練った対策方法と取るようにしていきましょう。



どんなジャンルで出題されても回答できるよう、小論文の書き方について勉強したり、どんなことにも自分の考えを持つトレーニングをしたりすることが重要ですね!
東京消防庁の小論文で差を付けるなら「東消塾」がおすすめ
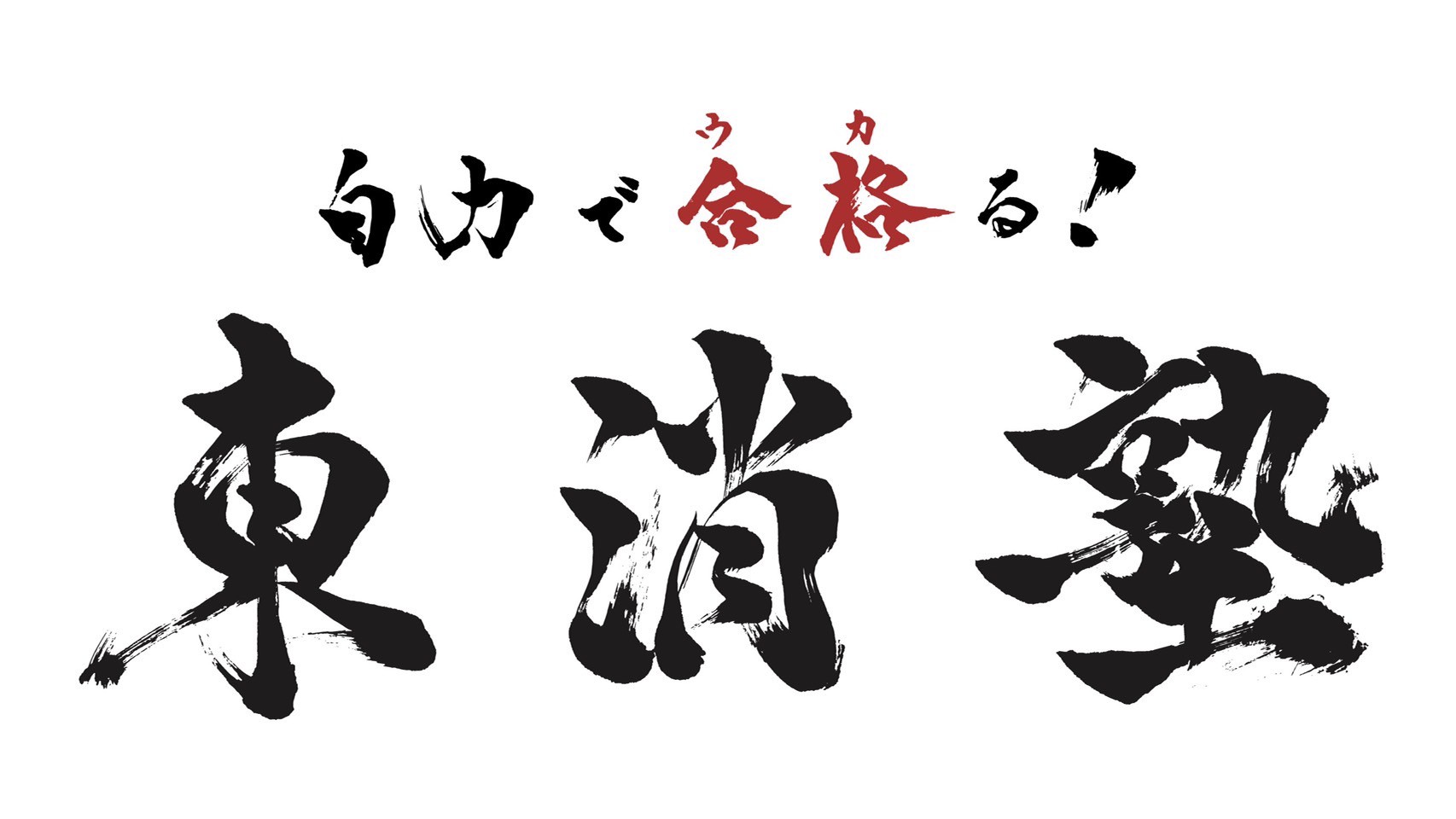
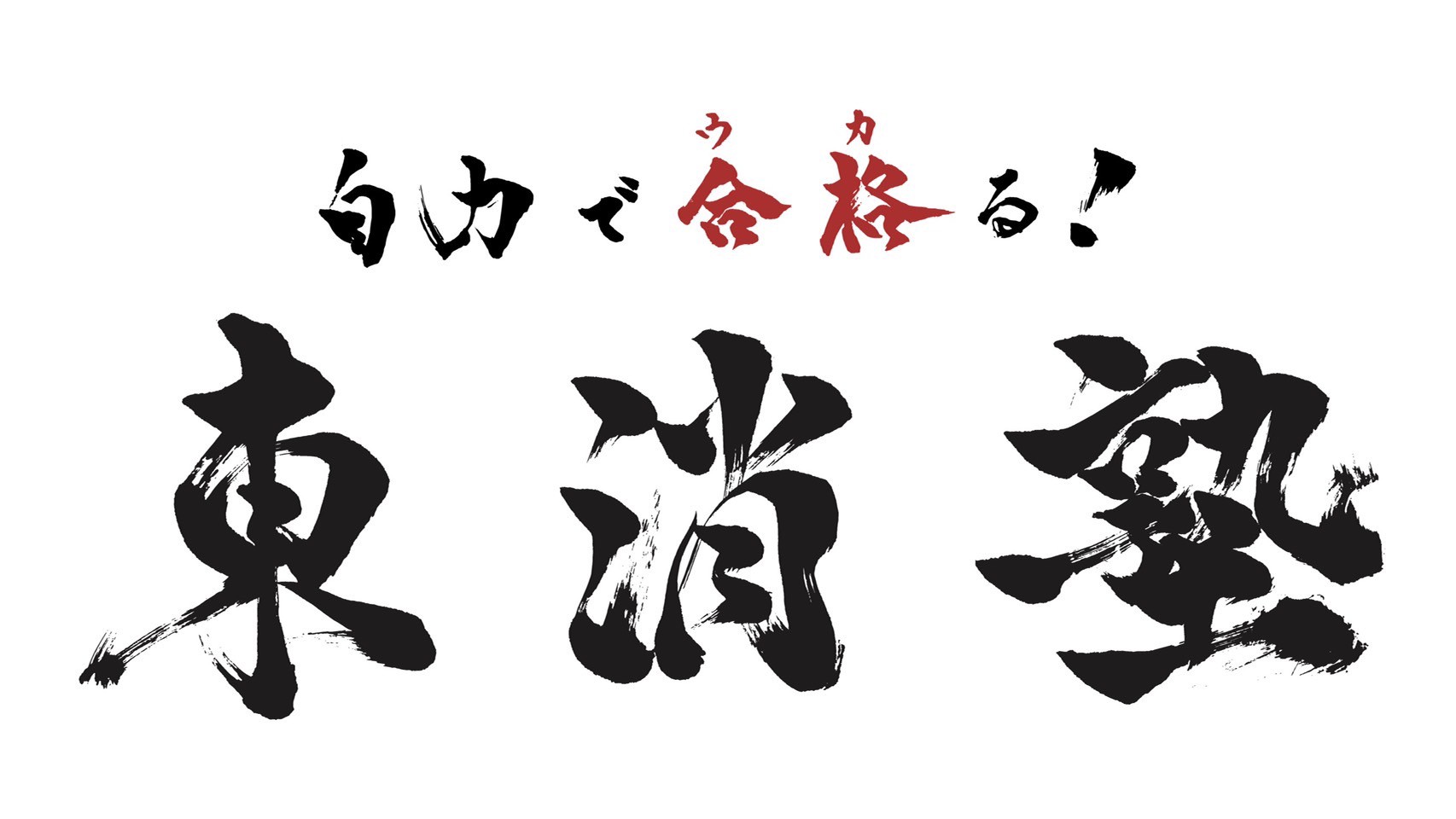
東京消防庁OBである私が運営する「東消塾」は、消防士試験の合格に特化したオンラインスクールです。
多くの受講者が東京消防庁をはじめ、さまざまな消防本部の採用試験に合格した実績があります。
勉強効率を上げるために個別の学習スケジュールを作成し、最短で消防士試験に合格できるように手厚くサポート。



いつから試験勉強を始めるべきなのか悩んでいる人や、独学での試験合格が不安な人は、まずは下記のボタンからLINE公式アカウントで無料相談をしてみましょう!
\どんな悩みでもまずは気軽に無料相談!/
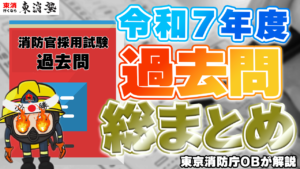
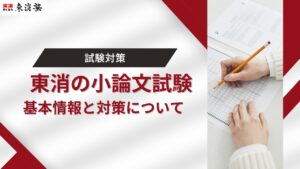

コメント