 TOMO LABO
TOMO LABO東京消防庁の試験対策に特化したスクール「東消塾」を運営している、TOMO LABOです!
総務省が発表するデータによると、令和5年4月1日現在、全国の女性消防士の数は、消防士全体の約3.5%となっています。
消防士はとても人気のある職業ですが、まだまだ男性中心の組織です。そんな中で女性が働くとなると、大変なことも多々あるでしょう。
今回は、女性消防士が必要とされる理由や女性消防士にしかできないこと、女性消防士になるのに必要な条件などを解説します。この記事を参考にすることで、女性消防士を目指す方の悩みを全般的に解決できるでしょう。
\消防士に関する情報を定期的に発信中/
女性消防士が必要とされる理由


女性消防士が必要とされる理由は、以下の3つです。
- 女性にしかできない役割があるから
- 組織全体の活性化に繋がるから
- 今後の女性消防士の目標となれるから
「災害現場で活躍するのは力のある男性だけ」と偏見を持っている方もいますが、力を発揮すること以外でも消防士として活躍できる場面は多いです。「女性だからできない」ではなく「女性だからこそできること」を理解すれば、女性消防士が必要とされる理由も理解できるでしょう。



女性消防士を目指す方だけでなく、男性も理解しておくべき項目となります!
女性にしかできない役割があるから
女性消防士は、男性消防士にはできない仕事や役割が担えます。
- 女性の被救助者に対してプライバシーの配慮ができる
- 女性や小さな子どもの被救助者をより安心させられる
- 女性向けの防火・防災教育や啓発活動において、効果的な支援ができる
- 職場内のセクハラ・パワハラ問題に対する意識が高められる
上記のように、女性ならではの視点で物事を考えられるため、救助活動や予防活動において、男性以上に的確なアプローチができる場面が生まれます。
女性消防士の意見は非常に貴重になるため、しっかりと知識や経験値を高めることで、より発言権が増していくでしょう。



もちろん消防士になりたての頃からできることではありませんが、目標を持って仕事に取り組めば、いつか必ず自分にしかできない役割が見つけられます。
女性の被救助者に対してプライバシーの配慮ができる
災害や事故の現場では、被害者のプライバシーに最大限の配慮が求められます。
女性の被救助者の中には、男性の消防士が身体への接触や着替え、処置に対応することに心理的負担を感じるケースもあります。そんな時に女性消防士が対応することで、同性ならではの安心感を与えられ、心理的抵抗を軽減することが可能です。
また、救急現場での女性の傷病者に対しても観察や応急処置などで安心感を与えながら対応できるため、活動をスムーズに行いやすくなるでしょう。
女性や小さな子どもの被救助者をより安心させられる
女性や小さな子どもは、緊急事態において強い不安や恐怖を感じることがあります。こうした場面でも、女性消防士が現場にいることで相手に与える印象が柔らかくなり、心を開きやすくなる傾向があります。
女性ならではの細やかな配慮と共感力は、災害現場での被救助者とのコミュニケーションにも大きく貢献し、円滑な支援に繋がるでしょう。
女性向けの防火・防災教育や啓発活動において、効果的な支援ができる
消防の仕事である防火・防災教育では、家庭内での防災意識を高めるための活動も行います。ターゲットが主婦層や子育て世代の女性になることも多いため、同じ女性消防士が講師となることで共感を得やすくなり、防火・防災教育の効果を高めやすくなります。
また、女性視点での具体的なアドバイスも可能となり、啓発活動の効果向上にも繋げやすくなるでしょう。
職場内のセクハラ・パワハラ問題に対する意識が高められる
消防士は力仕事ということもあり、男性の比率の方が多いのが現状です。ただ、男性中心だった消防の現場に女性が加わることで、多様性への理解が進み、職場の意識改革に繋がりやすくなります。
性別に関係なく全員が働きやすい環境を整えるためには、セクハラやパワハラへの適切な対処が不可欠です。女性消防士が増えることで、組織全体のハラスメント問題に対する意識が高まり、より健全で風通しの良い職場作りが促進されるでしょう。
組織全体の活性化に繋がるから
女性消防士がいることで組織全体の活性化に繋がることも、女性が必要とされる理由です。これまで男性中心だった消防組織に、女性目線での多様な考え方やアプローチが加わることで、チーム内の柔軟な発想や協力体制が生まれやすくなります。
また、男女が協働する環境が当たり前になることで、互いを尊重し合う文化が育ち、風通しの良い職場作りが進みます。風通しの良い職場は、組織の適応力や問題解決力を高める要素にもなり、より持続可能で強い消防組織を築くことに繋がるでしょう。



職場に女性がいるといないとでは、雰囲気が全然違うんです!
今後の女性消防士の目標となるから
現代は徐々に男女平等の社会に変化していますが、消防組織の中ではまだ女性の活躍する場は少ないという声が多いのが現状です。
男性主体の組織である消防組織の中で女性消防士として働く姿は、今後消防士を目指そうとしている女性の助けになります。
また、女性消防士がいることによって昔ながらの暗黙の了解のようなものも解消され、風通しの良い働きやすい職場となるでしょう。



これから女性消防士を目指す方の目標となれることでしょう!
女性消防士の現状と割合


男性の多い消防組織ですが、女性消防士の積極的な採用が進んでいるのが現状です。女性消防士の現状の人数と割合は、以下の表を参考にしてください。
令和5年4月1日時点で女性消防士の数は5,829人となっており、全体の3.5%を占めています。上記の表からもわかる通り、過去10年で2,118人増加しており、割合も1.2%増加しています。
今後はさらに増加することが予想されるため、女性消防士の活動領域が増えたり、働きやすい職場作りが進んだりする可能性が高いでしょう。



まだまだ全体で見ると少ないですが、徐々に増えているのが特徴です!
女性消防士が少ない理由


女性消防士が少ない理由としては、以下のようなものが挙げられます。
- 男性中心の職場環境であり身体的・精神的負担も大きい
- 女性消防士の雇用経験に乏しい消防署が多い
- 女性消防士に対するハラスメントが起きる可能性がある
女性が消防士として働こうと思ったとき、男性ではあまり感じない大変さ・難しさに直面することがあります。
しかしそれは決して女性消防士が悪いわけではなく、女性を平等に扱えない人や体制が悪いのです。
どんな大変さや難しさに直面するのか、詳しく解説していきます。
男性中心の職場環境であり身体的・精神的負担も大きい
女性消防士が増えているとは言っても全消防士の中で3.5%とまだまだ少なく、女性消防士が働きづらいと感じる場面も少なくありません。そもそも、消防のメインの業務は消火・救助・救急活動などであり、過酷な状況で身体的な負担が大きいものがほとんどです。
例えば、防火衣や空気呼吸器など活動時の装備だけでも約20kgあり、男性よりも筋力で劣る女性は男性と同じだけの仕事をなかなかできません。
また、男性消防士の中には女性消防士に対する理解が少ない方もいるため、精神的な問題を抱えることもあるでしょう。
以上のようなことからも女性消防士は男性よりも身体的・精神的負担を感じやすいため、女性消防士が少なくなる理由だと考えられています。



男女間で力の差があることなどはどうしようもないことです!
女性消防士の雇用経験に乏しい消防署が多い
職員数の少ない地方・田舎の消防署だと、女性消防士を雇用した経験のある消防署はほとんどないでしょう。
そのため、女性消防士に対するサポート体制が整っていない場合があります。
出産や育児に対する支援がないと、ずっと働き続けるのは困難です。
女性に対するサポートが充実している消防署となると、どうしても数が限られてきてしまい、職場選択の幅が狭まってしまいます。



都市部になればなるほど、女性消防士の雇用経験がある消防署も増えるでしょう。
女性消防士に対するハラスメントが起きる可能性がある
女性消防士が一生懸命仕事に取り組もうとしているなか、非常に残念ながら職場でハラスメントが起きる可能性があります。
ニュースでも度々女性消防士に対するパワハラやセクハラが報道されていますね。
女性消防士に落ち度は微塵もなく、パワハラ・セクハラをする相手が悪いにもかかわらず、泣き寝入りすることになったり、女性消防士のほうが退職することになったりするのが問題です。



パワハラ・セクハラを告発して、相手が懲戒処分になったとしても、その職場にいたくなくなってしまいます。
女性消防士になるのに必要な条件


女性消防士になるのに必要な条件は、特にありません。しかし、採用試験では性別に関係なく公平な採点がされるため、受験前に知っておくべき部分もあります。
女性消防士を目指している方は、消防官採用試験を受験する前に以下の2つを理解しておきましょう。
- 身体基準や必要な体力
- 女性消防士の合格倍率
女性消防士の採用における現状を理解しておくことで、適切な対策を立てやすくなり、採用試験の合格率も高められるでしょう。



身長制限のような絶対条件は必ず確認しておきましょう!
身体基準や必要な体力
消防官採用試験は、年齢や国籍などをクリアしていれば誰でも受験可能です。ただ、多くの消防本部で2次試験に「身体検査」や「体力試験」が行われます。
女性で消防士を目指す方は、この2つを不安に感じている方もいるでしょう。東京消防庁を例に、身体検査と体力試験の内容を確認しておくことが大切です。
| 視力 | 視力(矯正視力を含む。)が0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上。 なお、裸眼視力に制限はありません |
|---|---|
| 色覚 | 石原式色覚検査を実施します。 ※石原式色覚検査で異常があった場合は、赤色、青色及び黄色の色彩識別検査を実施します。 ※色彩識別検査で異常があった場合は、後日、眼科医による診断を受けていただきます。 |
| 聴力 | オージオメータを使用し、純音聴力検査を実施します。 |
| 体力 | 1km走、反復横とび、上体起こし、立ち幅とび、長座体前屈、握力、腕立て伏せにより体力検査を実施します。 |
| 健康度 | 尿検査、胸部X線検査、心電図、血液検査、血圧、問診により検査を実施します。 |
身体検査や体力試験は、男女関係なく同じ基準で評価する消防本部が多いです。女性の方が男性よりも筋力が少ない分、難易度が上がります。しかし、裏を返せば男女関係なく公平に評価されているとも言えるため、基準をクリアできるように準備しておくことが大切です。
消防官採用試験の体力に関して知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。


女性消防士の合格倍率
女性消防士を目指す方は、女性消防士の合格倍率を理解しておくことも大切です。東京消防庁を例とした合格倍率は、以下の表を参考にしてください。
| 受験者数 | 最終合格者数 | 合格倍率 | |
|---|---|---|---|
| 男性 | 2,328人 | 347人 | 14.9% |
| 女性 | 172人 | 32人 | 18.4% |
参考:職員採用選考・試験結果 | 東京消防庁
上記の表は、東京消防庁の令和5. 6年度の数値を参考に算出したものです。
男性の合格倍率が14.9%なのに対し、女性の合格倍率は18.4%となっています。現状で約5人に1人が合格できるだけでなく、今後の積極的な採用を踏まえると、さらに合格しやすくなるとも考えられるでしょう。
消防士を目指す女性へのアドバイス
「働きづらさを感じることになっても、本気で消防士を目指したい」という熱意ある女性は、消防士を目指すうえで、以下のことに力を入れておくと、働きやすさが向上することでしょう。
- 体力・筋力トレーニングを継続する
- 業務に関する資格や技能の習得を目指す
- 心身の健康に気を配る
少しでも楽しく仕事をするために、今のうちからできることを始めてみてください。
体力・筋力トレーニングを継続する
消防士の仕事は、過酷な状況下での活動が多いため、体力や筋力が重要です。
特に女性は筋力で男性に劣ってしまうため、男性と同様の業務をこなすには、定期的なトレーニングをおこない、体力や筋力を維持・向上しておく必要があります。
そもそも採用試験には体力試験があるため、消防士を目指そうと考えているなら今のうちからトレーニングを始めましょう。



消防士になってからは、訓練やトレーニングの時間にある程度体力・筋力は付きます。
業務に関する資格の取得を目指す
消防士として女性が働くのは難しいと言われていますが、消防業務に関する資格を取得することで、職場での競争力を高められます。
消防士になってから習得するのにおすすめの資格をまとめました。
- 大型自動車免許
- 救急救命士
- 危険物取扱者
- 陸上特殊無線技士
- 予防技術検定
上記の資格は、基本的には消防士になってから取得します。
救急救命士は取得するまでにキャリアが必要になってくるため、消防士になる前に専門学校や大学で取得する人も。
資格を取得することで手当が増え、年収アップにもつながるため、消防士として活躍していきたい女性は、業務に関する資格を積極的に取得していきましょう。



業務経験を積み、資格も取得している消防士は、署内でも重宝する人材になります。
心身の健康に気を配る
消防士の仕事は、心身ともにかなりの負荷がかかることがあります。
特に女性消防士は、職場での理解や支援が不十分な場合があるため、日頃から心身の健康に注意を払うことが重要です。
助けを求められる職場環境であればそれに越したことはありませんが、もしそうでない場合、自分自身でストレスを解消する方法を見つける必要があります。
幸いなことに消防士は休みが多い仕事なので、なるべく休日は趣味に打ち込んだり、心を許せる人と一緒に過ごしたりして、良好な精神状態を保つようにしましょう。



実は消防士の休日数はとても多く、1年の約2/3が休みになっています!
東京消防庁は女性消防士への支援が充実している


筆者が過去に勤めていた東京消防庁では、女性消防士への支援が、他の消防本部と比べて非常に充実しています。
東京消防庁が公式ホームページで公表している「両立支援制度」を、以下にまとめました。
- 妊娠出産休暇
-
出産前後で、最大16週休暇が取得可能。
- 育児休業
-
出産後、最大3年間の育児休暇が取得可能。
- 育児短時間勤務
-
週3日で8時間勤務、週5日で5時間の勤務など、出勤時間・日数を状況に合わせて選択可能。
- 部分休業
-
子育ての状況により、出勤前後で最大2時間以内の部分休業が可能。
出産や子育ては、生活や働き方に大きな影響を及ぼします。
そのような中でも東京消防庁では、女性の支援が充実しているため、安心して消防士としての職務に励めるのが嬉しいですね。



育児休業の取得率は100%です!
東京消防庁の女性消防士の割合
東京消防庁では近年、女性消防士の採用を積極的に行っています。東京消防庁の女性消防士の割合推移に関しては、以下の表を参考にしてください。
| 女性消防吏員割合 | |
|---|---|
| 令和6年4月1日 | 7.16% |
| 令和5年4月1日 | 7.09% |
| 令和4年4月1日 | 6.93% |
| 令和3年4月1日 | 6.84% |
| 令和2年4月1日 | 6.76% |
| 平成31年4月1日 | 6.66% |
| 平成30年4月1日 | 6.53% |
| 平成29年4月1日 | 6.54% |
| 平成28年4月1日 | 6.39% |
| 目標:令和8年度当初までに8%以上 | |
東京消防庁において、平成28年時点での女性消防士の割合は6.39%だったのに対し、令和6年度の女性消防士の割合は7.16%となっています。令和5年時点での東京消防庁の職員数は18,684人であり、割合から計算すると女性消防職員は1,338人です。
参考:組織 | 東京消防庁
割合で見ると少ないですが、人数だと1,000人を超えているため、これから女性消防士を目指す方も心強いでしょう。



女性消防士がどれぐらい在籍しているかを知っておくことも大切です!
東京消防庁における女性消防士の勤務体制割合について
消防士には、シフト勤務となる「交代制勤務」と、一般企業と同じく朝から夕方まで、月〜金曜で働く「毎日勤務」の、2種類の勤務体制があります。
「交代制勤務」は、消防・救助・救急活動などをおこなう、一般的なイメージの消防士の働き方で、「毎日勤務」は、消防活動はおこなわず、事務仕事が中心となる働き方です。
東京消防庁において、「交代制勤務」をする女性消防士の割合は28.2%、「毎日勤務」をする割合は71.8%となっています。



2種類の働き方から、自分に合ったほうを選びましょう!
女性消防士に関するよくある質問


女性消防士に関するよくある質問をまとめたので、気になる方は参考にしてみてください。
まとめ:働くのが難しいと言われる女性消防士にしかできない仕事がある
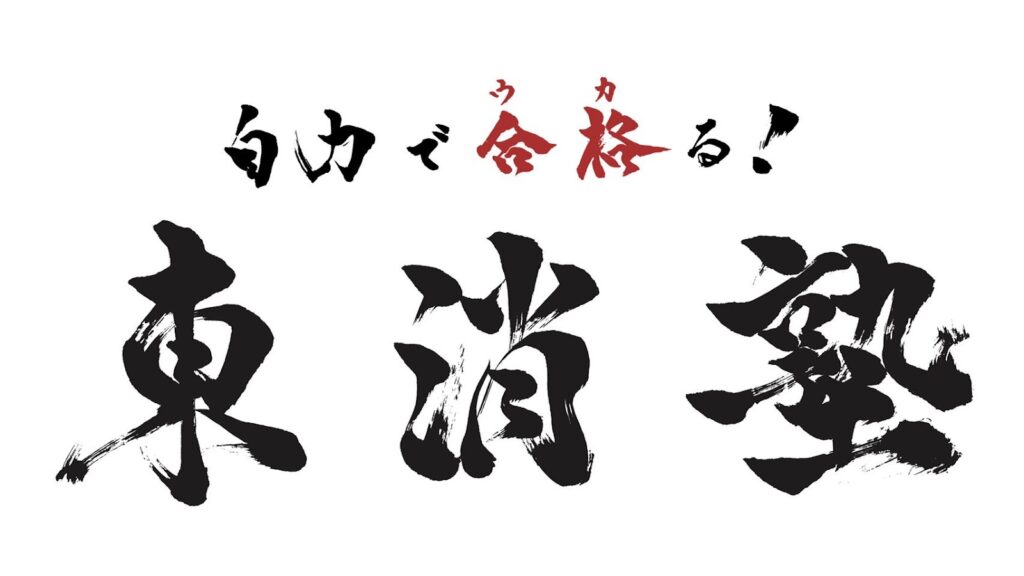
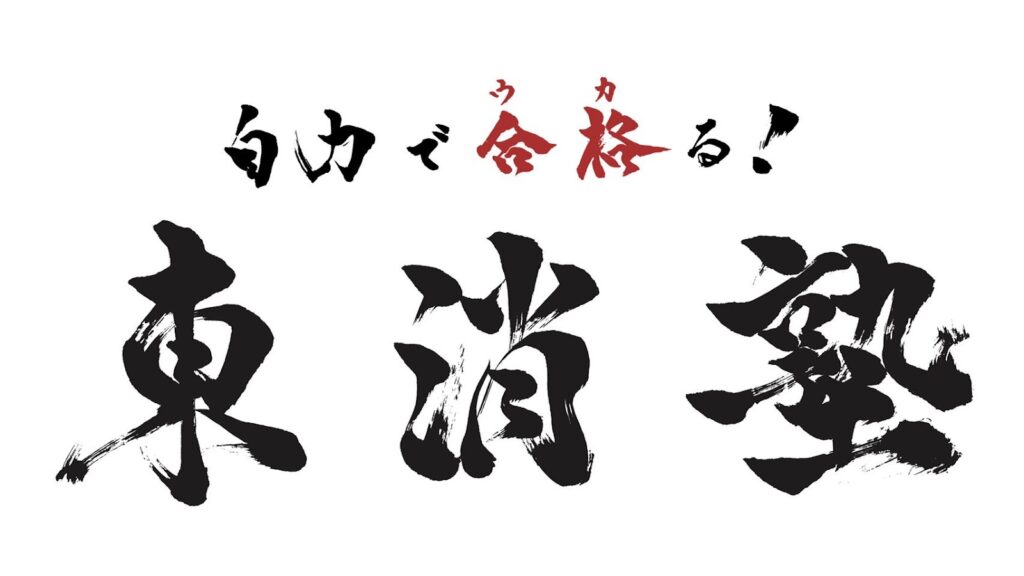
悲しいですが、女性消防士が働きづらさを感じる職場が存在するのは事実です。
女性消防士の雇用経験がない職場で働くのは、心身ともに強いストレスがかかってしまうリスクがあります。
しかし、東京消防庁は女性を支援する制度が整っているため、女性にしかできない仕事ができ、自分の力を存分に発揮できる環境です。
女性消防士として気持ちよく仕事がしたいという人は、ぜひ東京消防庁を目指してみてはいかがでしょうか。



東京消防庁の採用試験合格に特化した「東消塾」では、元東京消防庁職員があなたの夢を徹底サポート!
🧑🚒 Aさん(大学4年・東京消防庁志望)
面接対策動画を見て、自分の伝え方が明確に変わったのを実感しました。志望動機の深掘りの方法や、話すときのポイントがとても分かりやすくて、自信が持てるようになりました。本番の面接が楽しみになるなんて、正直びっくりです。
👩🚒 Bさん(社会人・転職希望)
小論文対策の動画は「今まで何となく書いていた」自分にとって衝撃でした。テーマの捉え方から構成の作り方まで丁寧に解説してくれて、考えを文章にする力が身についた感じがあります。添削されなくても改善点が分かるようになりました。
👨🚒 Cさん(専門学生・筆記苦手)
筆記試験がネックでしたが、LINEでもらった動画で解き方のコツを学べて、ぐっと理解が深まりました。特に数的処理の「考え方のパターン」を教えてくれるのがありがたくて、過去問を解くスピードが確実に上がっています。
\女性消防士の悩みも無料で相談可能/



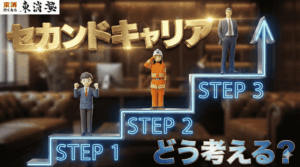


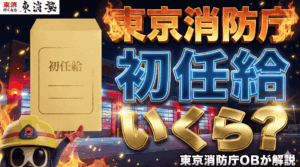
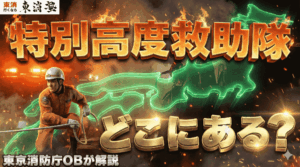



コメント