 TOMO LABO
TOMO LABO元東京消防庁職員で、現在は消防士の採用試験合格に特化したオンラインスクール「東消塾」を運営している友口です!
この記事を読んでいるあなたの周りにも、消防団に入っている人が何人かいるのではないでしょうか。
消防団員たちが訓練したり活動したりする話を聞き、消防士とどう違うのかという疑問が浮かぶ人も多いはずです。
そこで今回の記事では、消防士と消防団員は何が違うのかを、消防団の基本的な知識と併せてご紹介していきます。
\消防士を目指す人が知りたい情報を発信中/
そもそも消防団とは?


消防団は、消防組織法に基づいて各地域に設置される消防機関です。
消防団に入団すると、非常勤の地方公務員となります。
地方公務員といっても特別職という枠になるため、地方公務員法は適応されません。
団員は全員、消防以外の本業を持っているため、基本的にはボランティア精神に基づいて活動しています。
消防団の入団資格
消防団員の入団資格は、各市町村ごとに条例で定められており、地域によって多少違いがあります。
一般的には18歳以上であり、その市町村に居住している人や、勤務・通学をしている人であれば、職業や性別を問わず誰でも入団可能です。
一般職の公務員は基本的に副業禁止とされていますが、消防団への入団は認められています。



僕の友人にも何人か消防団に入っている人がいました。ほとんどが男性でしたが、女性で入団している人もいます。
消防団への入団方法
前述の総務省消防庁の公式サイト、もしくは各市町村の公式サイト内に記載されているメールアドレス・電話番号から、入団希望の問い合わせをしましょう。
オンラインの応募フォームはありません。
職員に対応してもらい、無事に入団手続きが完了すれば、あなたも消防団員の一員です。
もしも家庭や仕事の都合で定期訓練・活動にあまり参加できない場合は、入団を受け付けてもらえない場合があるため注意が必要です。
消防団員の仕事内容
消防団員は、消防士が活動する際の補助や交通整理などが主な仕事です。
消防士が到着する前には、火災時の出動であれば消火活動、地震や風水害などの自然災害時の出動であれば救助・救出も行います。
また災害発生時以外では、各家庭に訪問し防火指導をしたり、防火設備の点検をしたりと、啓蒙活動も行います。
各市町村で回数は異なりますが、活動するのに必要な知識・経験を得るための座学や訓練があるため、現場に立つなら参加は必須です。



制服や靴などは個人貸与もしくは備品として貸出されるため、私服のまま活動する危険性はありません!
消防団員の待遇
多くの自治体では、消防団員であることに対する「年額報酬」(5万円程度/年)と、災害や訓練時に出動した際の「出動報酬」(災害は8,000円程度/回、災害以外は4,000円程度/回)が貰えます。
5年以上消防団員として活躍し退団した際には、退職報償金(20〜100万円程度)が支給されるのも嬉しいポイントです。
もしも活動中に負傷した場合には、公務災害補償金(8,000〜15,000円程度)の対象にもなります。



活動で功労や功績を上げた人は、表彰される場合も!報酬は各市町村で異なるため、詳しく知りたい人は最寄りの役所に問い合わせてみましょう。
消防士と消防団員の違いや関係性を解説


消防士と消防団の違いや、後述する消防署と消防本部の違いは、消防組織法によって定義されています。
消防組織法をもとに、それぞれどのような違いがあるのかをまとめました。
| 消防士 | 消防団員 | |
|---|---|---|
| 主な活動内容 | 消火活動や人命救助等 | 消防士が活動する際の補助 |
| 勤務形態 | 朝から夕方までの勤務で、事務が主な仕事の「毎日勤務」を取る職員と、24時間勤務を交代制で行う「交代制勤務」を取る消防吏員がいる。 どちらも消防署や消防本部に常勤している。 | 出動要請があれば現場に出向くが、基本的には本業が優先。 |
| 身分 | 常勤の地方公務員 | 非常勤の地方公務員(特別職) |
| 給料・報酬 | 給与+各種手当 | 年額報酬+出動報酬 |
| なり方 | 消防士採用試験に合格する | 消防団に入団申請をする |
消防団に関するQ&A
消防士・消防団員の違いと関係性についてのまとめ
消防団員について知っておきたいことのまとめです。
- 消防団員は、本業を別に持ちながら消防活動も行う、非常勤の地方公務員(特別職という扱い)
- 18歳以上でその市町村に居住・通学・通勤していれば基本的には誰でもなれる
- 消防士の活動補助が主な仕事
- 活動に必要な座学・訓練を受ける必要がある
消防団はボランティア的な精神のもとで活動する組織であるため、年々団員が減少しているそうです。
もしこの記事を読んで興味を持ったならば、今あなたが住んでいる市町村に問い合わせをしてみましょう。



当ブログでは「消防士とはどんな仕事か」も紹介していますので、消防団の延長線上で消防士という仕事に興味を持った人は、ぜひ他の記事も読んでみてください。
\消防士になろうか迷っている人はこちら/





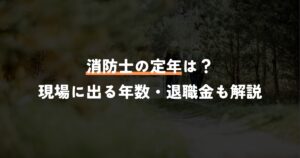
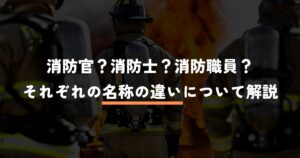
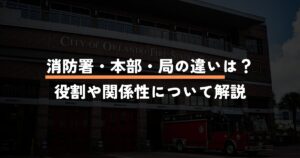
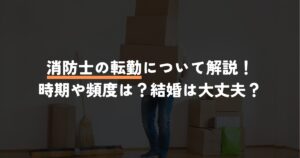

コメント